「何度言っても伝わらない」
「どうしてこんな結論になるのか分からない」
組織で働く中で、こうした“伝わらなさ”に悩んだ経験は、誰しも一度はあるのではないでしょうか。
その原因のひとつに、「思考スタイルの違い」があります。
とくに、教育や職種の背景にある“理系的”または“文系的”な考え方のクセが、日常的な認識のズレや誤解を生むことがあります。
「論理重視 vs 共感重視」すれ違いの典型例
会議で、数字を中心に論理展開するAさん(理系出身)。
一方で、現場の声や感覚的な判断を重視するBさん(文系出身)。
Aさんは「要点がまとまっていない」と感じ、
Bさんは「冷たくて融通が利かない」と不信感を抱く。
どちらも悪気はないのに、会話が噛み合わない。これはよくある構図です。
認知スタイルの違いは“正確性”と“納得感”のズレを生む
心理学ではこのような思考の傾向を「認知スタイル(Cognitive Style)」と呼びます。
- 理系的スタイル:前提条件の明確化 → 論理的な整合性 → 結論(結論主義)
- 文系的スタイル:状況や背景の共有 → 共感や全体像 → 行動(納得重視)
この違いが、
- プレゼンの組み立て方
- 会議での話し方
- 判断スピード
- 合意形成のしかた
などに影響を与え、知らず知らずのうちに**“わかり合えない構造”**を作ってしまいます。
組織に起きるリアルな影響
実際にこの“思考ギャップ”がもたらすのは、次のような現象です:
- ロジックで詰めすぎて、現場が委縮
- 空気で話す場面が多く、誤解が連鎖
- 「正論」と「共感」の板挟みで中間管理職が疲弊
論理と感覚は、どちらが正しいという話ではありません。
大切なのは、自分とは違う認知スタイルが存在するという“前提”を持つことです。
違いを翻訳できる人が、組織の潤滑油になる
どちらかの思考に偏るのではなく、相手のスタイルを理解し、それに合わせて伝え方を調整できる“翻訳者”が組織内にいると、
- 会議がスムーズに進む
- 決定が早く、納得感もある
- 現場と経営の接続がなめらかになる
といった効果が生まれます。
これは、管理職やチームリーダー、経営層にとって、これからますます求められるスキルだと感じます。
思考の違いを“個性”として受け止め、柔軟に翻訳しながら橋渡しできる人材は、組織の強さそのものにつながるのです。
最後に
組織内のコミュニケーションや認知スタイルの違いによる課題は、放置すれば摩擦や離職にもつながりかねません。
冨旺経営支援事務所では、中小企業診断士としての専門性を活かし、こうした“目に見えにくい組織のすれ違い”への対処や、人材育成支援などの経営コンサルティングも行っています。
お悩みのある企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
理解し合えないのではなく、「理解の仕方が違うだけ」。
この視点を持てるかどうかが、組織の風通しや成果に大きく影響します。
多様な思考スタイルを尊重し、橋渡しができる人材をどう育てていくか。
それこそが、これからの組織づくりにおける大きな鍵になるのではないでしょうか。

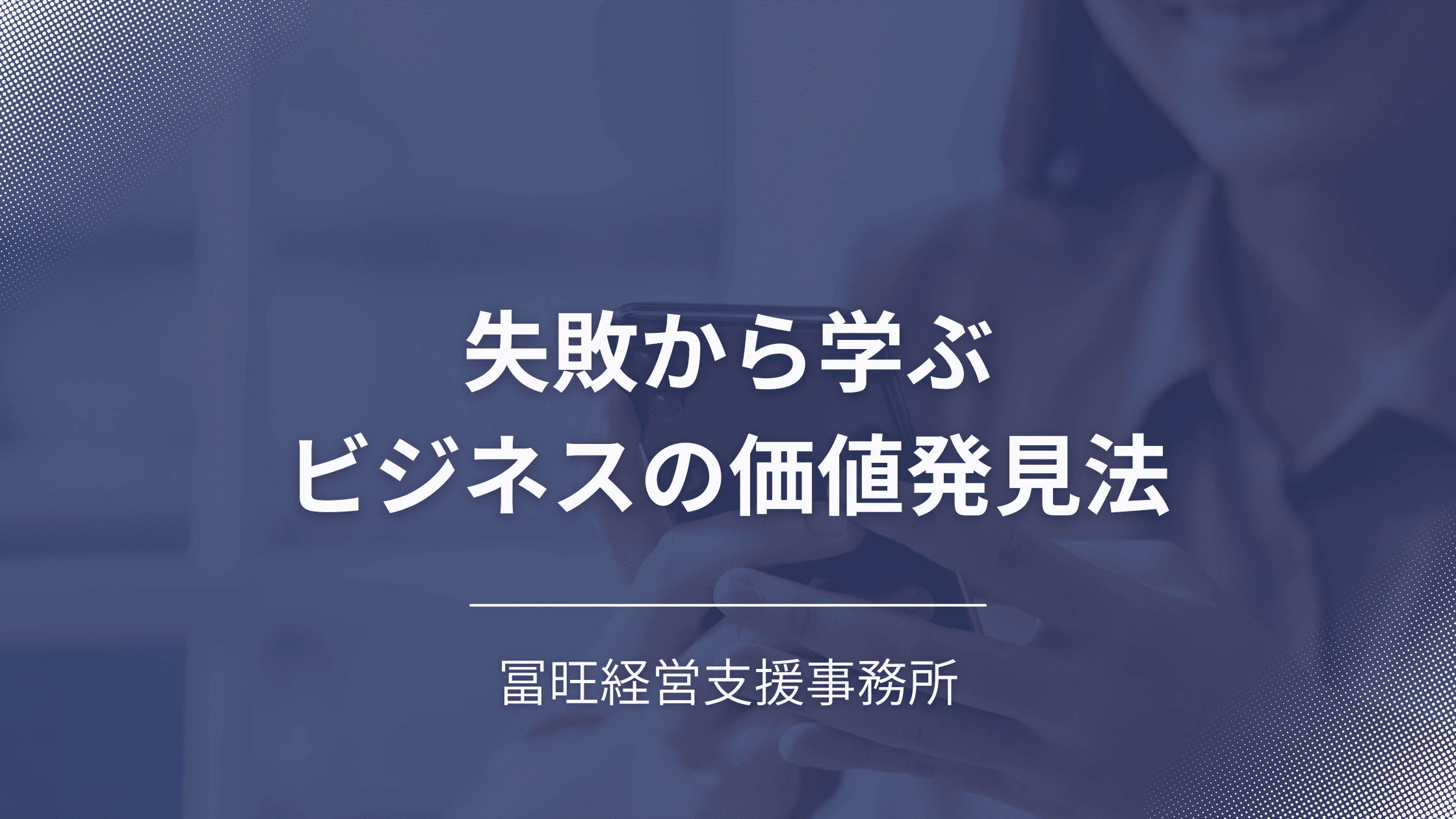
コメント