「成果を上げる人とそうでない人の違いは、どこにあるのか?」
この問いに対し、私たちは一つの確信を持っています。
それは――**“前例のない挑戦を恐れず、実行に移せるかどうか”**です。
中小企業の経営現場でも、支援の場面でも、前例がない取り組みはしばしば敬遠されがちです。リスク、不確実性、抵抗感…。確かに慎重さは必要です。
しかし実のところ、「誰もやっていないこと」こそが、成果を生む最大の起点であることが、近年の科学的知見からも示唆されています。
【1】人の脳は「意外性」に強く反応する(予測誤差理論)
脳科学の分野では「予測誤差(Prediction Error)」という概念があります。
私たちの脳は常に先を予測しながら行動していますが、その予測が外れると、脳内でドーパミンが分泌され、学習や記憶の活性化が起こります。
言い換えれば、 “意外な出来事” や “予想外の失敗” こそが、脳を活性化し、新しい学びや気づきを促すのです。
✅ つまり、常識にとらわれない発想やアプローチは、相手の記憶に残りやすく、自分自身の学習効率も高めてくれます。
【2】革新はいつも「外れ値」から始まる(破壊的イノベーション)
経営学の、クレイトン・クリステンセン教授が提唱した「破壊的イノベーション」理論では、
従来の成功モデルの延長線ではなく、市場の外側や未成熟な領域から革新が生まれることが強調されています。
✅ 小さく、ニッチで、注目されないような試みこそが、やがて社会全体を動かす大きな成果へとつながる――このような事例は枚挙にいとまがありません。
【3】進化もまた「異端」から生まれる(突然変異と適応)
生物学の世界では、進化の過程において“突然変異”が新たな適応力を生む重要な起点となっています。
同じように、ビジネスにおいても、何が成功するかは実行してみなければわからないという側面があります。
✅ 過去の成功事例をなぞるだけでは、思わぬブレイクスルーにはつながりません。
【結論】繰り返しと実験こそが成功を導く
人と違う視点を持ち、小さく試して、失敗して、また修正して……。
このような「試行の繰り返し」こそが、成果を引き寄せるための王道です。
もちろん、大胆なチャレンジには勇気が必要です。しかし、一歩踏み出すことでしか得られない学びや気づきが、確実にあります。
実験的な姿勢を持つ人は、最終的に人よりも早く、深く、確かな成果に辿り着くのです。
【最後に】
現場ではよく聞かれる言葉があります。
「それ、前例はあるんですか?」
確かに前例は安心材料になります。しかし、前例がないからこそ、挑戦する価値がある。
その視点を持てる人や企業が、これからの時代を切り拓いていくのではないでしょうか。

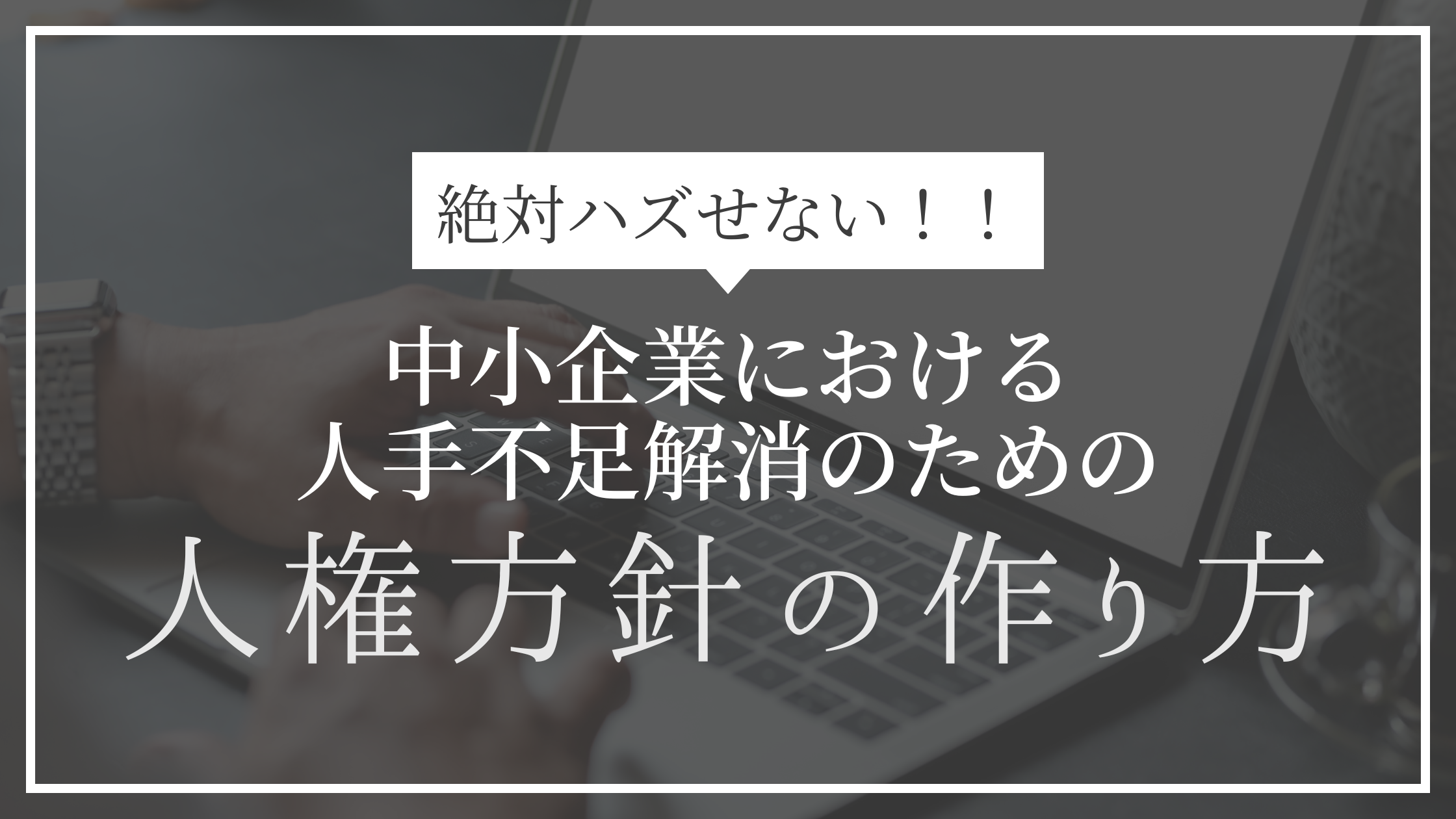
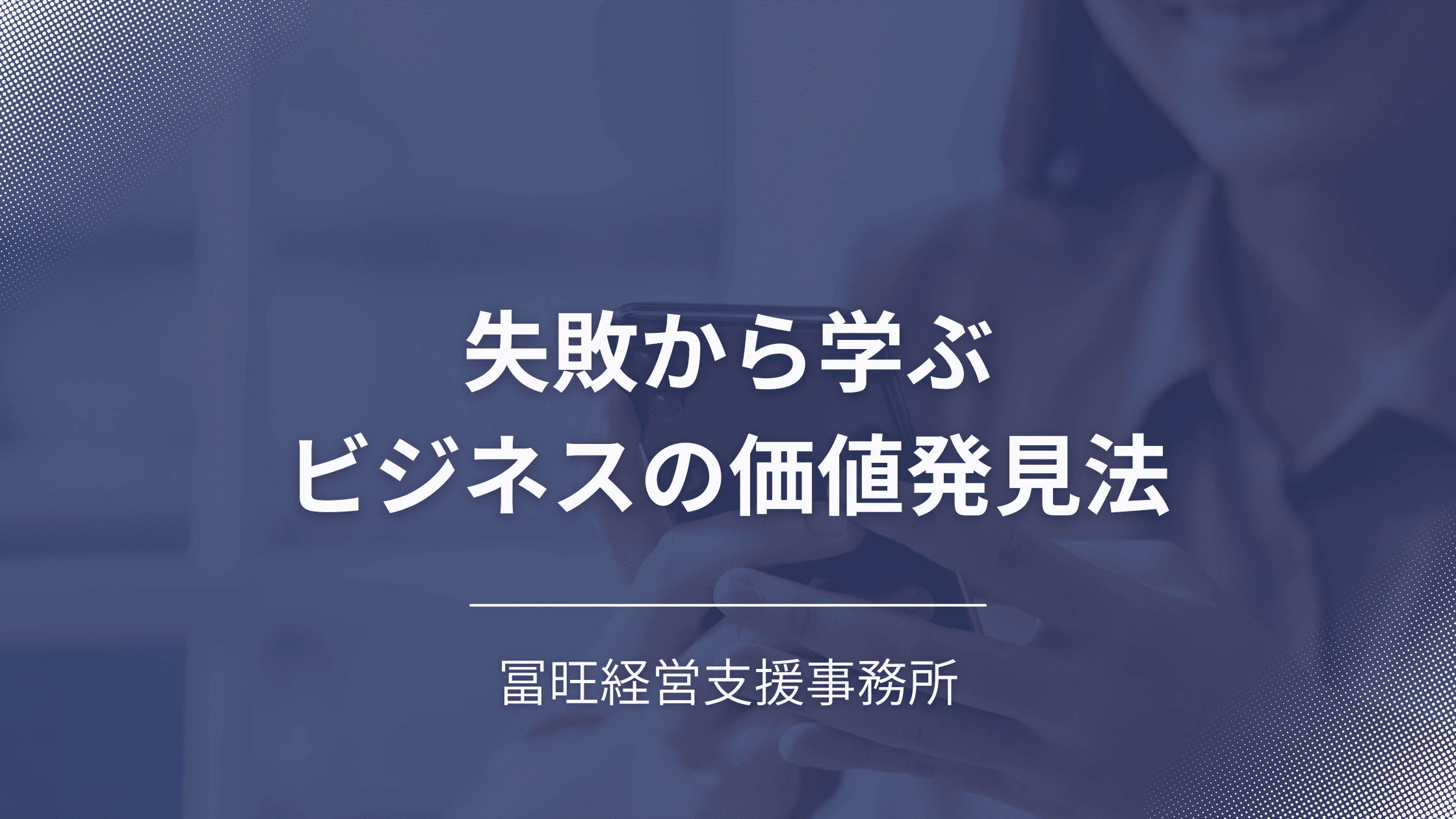
コメント